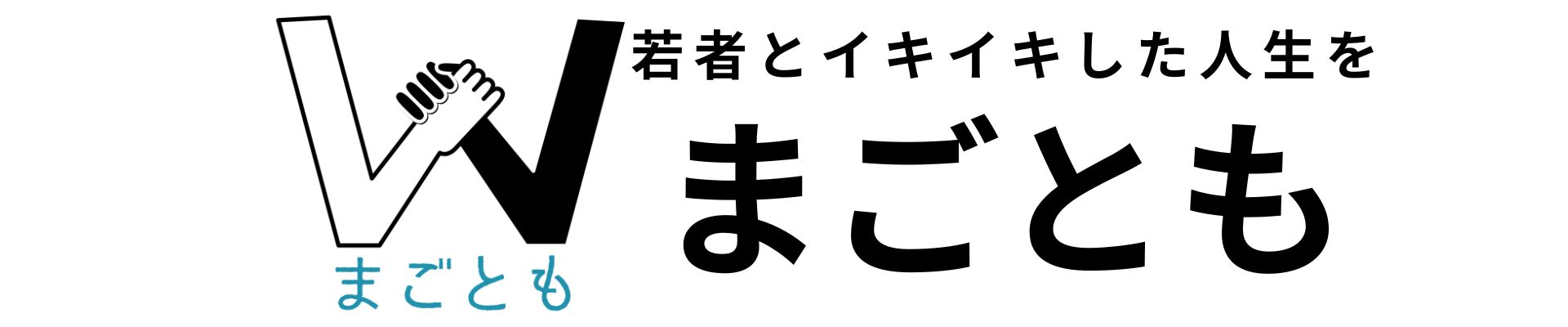とどまることなく少子高齢化が進む日本社会。
その状況下では、介護が必要な人の数はどんどん増えていくことが予想されます。
介護サービスを受ける際、在宅で介護を受けたいという高齢者の割合が多くなっています。
その動向に伴って在宅介護・ケアを行う介護者の需要も高まっていきます。
しかし昨今では、
在宅介護者の主観的幸福度が下がっているのではないかという研究がなされています。
そこで今回は、
「在宅ケアにおける介護者の負担度と主観的幸福感に関する研究」という論文を引用し、
在宅介護者の負担度と主観的幸福について考えていきたいと思います!
今回ご紹介する参考文献はがっつり論文で自力では読みにくいところもあると思いますが、
執筆者が解説を交えつつ要点をまとめるので安心してください!
ぜひ最後までご覧ください!
介護者の健康に対するケアが足りない!

この論文では、研究のきっかけが以下のように述べられています。
「近年、老人人口およびそれに伴う長期臥床〔がしょう〕患者や独居老人の増加に伴い、
在宅ケアの必要性が急速に高まっている。
そうした中、在宅ケアにおける患者 (以下被介護者) の健康に関する把握は従来よりなされているが、
それを看る介護者の健康に関わる環境要因の把握は未だ十分ではない。
核家族化や介護者自身の高齢化が目立つ状況下、
介護者の負担をいかに軽減できるかも在宅ケアを進めていく上で重要な要因と考えられる。」
老人人口と長期臥床患者、独居老人の増加はみなさんの知るところですよね。
この論文が発表されたのは1999年と少し古いのですが、
当時から同じことが叫ばれていたのに現状はさらに悪化していると考えると少し怖いものがあります。
この論文の研究者も述べている通り、
在宅ケアにおける患者さんの健康把握に関しては介護者の責任感もあり、
丁寧になされていると執筆者もある程度感じているのですが(それでも問題点がないとは言いません)、
介護者自身の健康に対するケアは十分になされていないのではないか、というのにも同感です。
核家族世帯(親と子供だけからなる世帯)や介護者自身の高齢化は1999年より深刻化しています。
在宅介護者の需要が高まる現代において、
介護者のケアは被介護者のケアと同等に重要です。
では、介護者の負担度と幸福感にはどのような関係があるのでしょうか。
家族間の在宅介護はどんな人が担っている?

この調査では、愛媛県のとある病院の訪問診療・看護を受けている高齢者、
長期臥床患者 (以下被介護者) の家族で、1年以上常に患者の介護にあたっている介護者20名に対して、
自分の主観的幸福度を調べています。
この調査対象について、論文ではこのように情報が残っています。
「介護者については、被介護者が男性例では7例中6例までが高齢の配偶者であり、
介護期間は3.2年、女性例では夫が2名、嫁が残り11名であり、
介護期間は6.9年と前者よりも長い傾向を認めた。」
(執筆者注:介護期間の標準偏差を除きました。数字は平均値です。)
つまり、介護が必要な男性に対しての在宅介護はほとんどの場合、
高齢の配偶者、つまりその男性の妻が担っているのに対し、
介護が必要な女性に対しての在宅介護は夫が担っていることは少なく、
むしろ息子の妻が担っていて、
さらにその場合には介護時間が長いという傾向があったそうです。
執筆者の感覚からすると、夫側が介護に非協力的であることに驚いてしまいました。
夫側に介護ができない事情があるのかもしれませんが…
1999年当時では、まだ性別による仕事と家事の分担の価値観が強かったのかもしれません。
そういえば、女性が夫に求める条件の1つに
「長男でないこと」
があると聞いたことがあります。
それは夫の親の介護をする可能性が低いからだそうです。
ということは、やはり親の介護は息子の嫁がするもの、という認識は存在するのかもしれません。
被介護者の年齢と介護負担度・主観的幸福感との関係
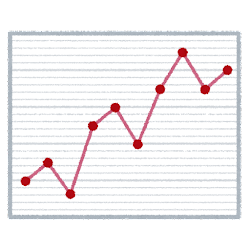
被介護者の年齢と介護負担度、主観的幸福感にはどのような関係があるのでしょうか。
体感では、被介護者の年齢が上がるごとに介護負担度は増加するように思えますが、
主観的幸福感はあまり予想できませんね。
論文では以下のように述べられています。
「被介護者の加齢と共に得点は有意に増加したが (r=0.518, p<0.05)、
主観的幸福感ではそうした関係はみられなかった。」
(執筆者注:rは相関係数。r=0.518はやや強い正の相関を示す。
pはp値。 p<0.05は95%以上の確率で被介護者の加齢と介護負担度が無関係でないことを示す)
つまり、被介護者の年齢が上がれば上がるほど介護負担度も増加していくのに対し、
加齢が主観的幸福感に影響を与える可能性は低いということがわかりました。
確かに年齢が上がるにつれて介護しなければいけないことも増えるでしょうし、
負担度が加齢に連れて増加してしまうのは仕方のないことかもしれません。
しかし、幸福感に関する結果を見ると、たとえどれだけ高齢の方を介護する場合でも、
やり方次第では主観的幸福感を高めることは不可能ではなさそうです。
介護者・被介護者の基本的属性と介護負担度との関係

次
に、介護者と被介護者がどのような人物であるか、という要素と、
介護負担度の関係を見ていきます。
こちらも体力や体調を考慮して、
女性の方が介護をするにおいて負担が大きそうだと感じてしまいますが、
実際はどうなのでしょうか。
「介護者における負担度については、
介護者側では女性(p<0.05) ほど、
被介護者との人間関係や自身の健康状況が良くないほど (各々p<0.05)、
また手段的支援ネットワークや情緒的支援ネットワークでの
点数が低いほど(各々p<0.005, p<0.05)大きくなり、
被介護者側では年齢が高いほど (p<0.05)、ADLでは離床が困難であるほど (p<0.05) 大きかった。」
予想通り、女性介護者の介護負担度は大きいようですね。
さらに、これも用意の想像できますが、被介護者との人間関係や介護者自身の健康状態が悪いと、
介護負担度も大きくなります。もはや当然ですよね。
その下の手段的支援ネットワーク、情緒的支援ネットワークとは、
この研究においては以下に示す事項のことです。
手段的支援ネットワーク
①経済的に困っているときに助けになる人
②あなたが病気で寝込んだときに身の回りの世話をしてくれる人
③引越しをしなければならないとき、手伝ってくれる人
④わからないことがあるとよく教えてくれる人
⑤家事をやってくれたり、手伝ってくれる人
情緒的ネットワーク
⑥会うと心が落ち着き安心できる人
⑦気持ちの通じ合う人
⑧つね日頃あなたの気持ちを敏感に察してくれる人
⑨あなたを日頃認め評価してくれる人
⑩あなたを信じて思うようにさせてくれる人
⑪あなたの喜びをわがことのように喜んでくれる人
⑫個人的な気持ちや秘密を打ち明けることのできる人
⑬お互いの考えや将来のことなどを話し合うことのできる人
各々の項目の「いる」「いない」の選択肢の中で「いる」と答えた場合を1点として合計点を評価
確かにこれらの項目に当てはまる人が多ければ多いほど介護負担は小さくなりそうです。
いや、介護負担にとどまらず日常のすべてにおいて悩みが少なくなりそうですね。
また、被介護者の年齢が高いほど介護負担度が大きいことは先ほど見た通りで、
ADLは離床が困難なほど介護負担度が大きいこともわかりました。
介護者・被介護者の基本的属性と主観的幸福との関係

では、介護者・被介護者の属性は主観的幸福感とどのような関係にあるのでしょうか。
「介護者の主観的幸福感については、副介護者がいるほど (p<0.005)、
手段的支援ネットワークや情緒的支援ネットワークでの点数が高いほど (各々p<0.05) 大きくなり、
ADLでは情報の理解が可能であるほど (p< 0.05) 小さかった。」
言ってしまえば当然と思えることが並んでいます。
副介護者はいないよりはいたほうが良いに決まっていますし、
手段的支援ネットワーク・情緒的支援ネットワークも、
充実していれば主観的幸福感が高まることは言うまでもありません。
介護者の幸福感を上げるにはどうしたら良い?

これまでの結果を踏まえ、介護者の幸福感を上げるにはどうしたら良いでしょうか。
純粋に結果だけ見ると、
「介護負担度を減らせるよう、被介護者との人間関係を整え、自身の体調管理を万全にし、
信頼できて頼れる人を見つけましょう!」
という結論になってしまいます。
それが簡単にできたら苦労しません。
まして、介護者の性別や被介護者の属性はどうしようもない部分です。
そこで、まずは介護に割いている時間を少し減らしてみてはいかがでしょうか。
現代では介護サービスが充実していますし、
保険外サービスを使えば幅広い作業を任せることができます。
介護サービスを使うほどではない、介護保険では対応できないことをしてほしい、
という場合におすすめなのが「whicker まごとも」です!
「まごとも」とは、地域の大学生がシニアのみなさんのご自宅や介護事業所に赴き、
日常のお手伝いをしたり、レクリエーションをしたりして楽しい時間を提供します。
日常生活の動作が難しい方や、お部屋やお庭のお掃除なども承ります!
さらに、お散歩やお買い物、病院への付き添いも可能です!
お散歩で公園などに寄って、自然を摂取する健康的でちょっとした運動もできます!
ご利用いただいたみなさまには笑顔があふれ、
「若返った気持がする」というご感想もいただいています!
普段の雑務は「まごとも」に任せて介護を少し休んで、
自分の生活、幸福感を見直してみてはどうでしょうか。
ご家族の皆様や介護者のみなさま、
身の回りのお年寄りに「楽しい」をプレゼントしませんか。
ご連絡お待ちしております。
お問い合わせ:050-6863-7272
メールアドレス:whicker.jp@gmail.com